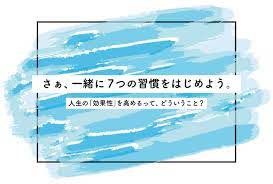「7つの習慣」は人が人らしく、自分らしい人生を生きるための、そして個人にも組織にも人間関係に置いても、長期的・継続的な効果(豊かで実りある人生)が得られる「原理原則」が描かれた書籍です。
原則とは・・・①万国共通で不変なもの
②質の高い結果を生みだすもの
③私たちの内面の外側にあるもの
④私たちが理解しなくても、受け入れなくても、必ず作用するもの
⑤自明的であり、理解すれば私たちに大きな力を与えてくれるもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これは「7つの習慣」でも言われていることですね。
私が思うに、読書することがP(心から望む成果)ではなくて、書籍の中から学んだことを人に伝えること=アウトプットすることが読書のPだと思います。
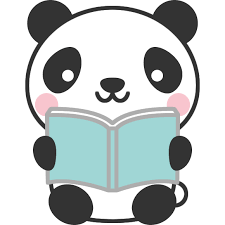 そのためには、日頃から本を読み込み、ブログやSNSを利用したり、直接誰かに伝えることがPを高めていくPC(そのために必要な能力やスキル)だと思います。
そのためには、日頃から本を読み込み、ブログやSNSを利用したり、直接誰かに伝えることがPを高めていくPC(そのために必要な能力やスキル)だと思います。
アウトプットがいかに大事かは、あらゆる書籍で述べられているのでここでは割愛させていただきますが、インプット2割・アウトプット8割くらいが理想とも言われています(パレートの法則??)。
話すことも、書くことも最初から上手にできる人などいません。話すことがうまい人はアナウンサーやコメンテーター、芸人などトレーニングを受けたり、毎日しゃべる練習をしている人たち。
書くことも同じです。作家のように毎日文章に触れ、考え、書き出す人たちや“書くことを生業”にしている人たち以外は、何千文字も何万文字も書いては消し、書いては消していくのかで「こういうことか」と肚落ちするときがやってきます。
私はいまだに話すことも、書くことも決して得意とは言えません。クラハでもスペースでも最初の数分間は緊張しております(なかなか信じてもらえませんが 笑)
ただし、自分の気持ちや考え・意見を人に伝えることは上手になって来たなとは思います。恐らく“共感による傾聴=アクティブリスニング”を日頃から意識して、実践し、その中で自分の意見もハッキリとわかりやすく、簡潔に伝えるスキルが高まって来たからだと思われます。
共感による傾聴=アクティブリスニングは、相手の話しを聞くだけではなくて、自分のことを伝えるトレーニングにもなるのです。まさに一石二鳥。
第5の習慣「まず理解に徹し、そして理解される」の「理解される」の部分ですね。
私の悪い癖として「7つの習慣」の話しになると、まず理解に徹しがすっ飛んでしまい、話したい=理解して欲しいという“ななちゅう病(7つの習慣中毒 笑)”が発症してしまうこと!
7SCのコーチングやるときとか、実践会のファシリテーターやるときは、そこが出ないように自分をコントロール出来ますが。
若いころに好きなギタリストの話しやバンドの話をしているときとまったく同じ症状が「7つの習慣」においても発症してしまいます(笑)
皆さんも大好きなこと、趣味のことになると、熱くなって延々と話したくなりますよね?同じです。
なんだか、アウトプットの大切さからすっかり脱線してしまいましたが、こんな形で思いつくままに書く日があっても良しとしてください。
普段は“考えながら”書いてはいるのですが、今日はアドリブで文章がどんどん出てきます。
「7つの習慣」について語ること・・・これは自分がもっとも伝えたいことなんだろうな!タイピングが止まりません(笑)
本日のまとめ・・・「インプットしたらアウトプットすることが大切です」
(連続投稿412日目)